柳下美恵のピアノdeフィルムvol.15『君と別れて』
柳下 「成瀬さんは、凄く静かな人だったと伺っていますし、撮影も定時に終わって、一人でお酒を呑むみたいなタイプだったということなので、そんな時に色々人間観察をしていたのですかね」
大久保 「エッセイで、人を観察したものをメモしているってことを書かれていますね(「成瀬巳喜男「ノートから」、『映画之友』1935年5月号。田中眞澄、阿部嘉昭、木全公彦、丹野達弥編『映畫読本 成瀬巳喜男――透きとおるメロドラマの波光よ』フィルムアート社、1995年に再録」)。女性の店員さんがテーブルを片付けるのとか、お客さんの仕草などを観察しては、メモに取っていたと。それらをどこかの演出で生かそうと考えていたのではないかなと思います。結構静かな方だったというのは、もう伝説のようになっていて、そこだけが独り歩きしてしまっているみたいなところもあるのですが、そういったことにあまり捉われずに観ていって、新しい刺激を受けてもいいと私は思ったりしています。」
柳下 「新しい刺激というのはどういうことですか」
大久保 「『君と別れて』で言うと、水久保澄子という女優さん、衝撃的と言ってもいいくらいの存在感があるのではないかという気がしますね。現代的といっていい容姿で、ぐれている少年義雄を母親の代理として善導していくところがあります。成瀬巳喜男という人の中では、あまり子供という意識がなかったのかもしれないですね。というのも、子供という概念は近代から出てきたものと言われていますし、成瀬巳喜男監督も15歳で松竹に入って、あまり少年時代というのを過ごすことができなかった人なのです。ずっと大人扱いされて生きてこなければいけなかったので、今から見ると子供を描いているように見えるのですが、彼から見ると、大人として子供が出てきているようにも見えます。そういう意味では『君と別れて』に関しては、ちょっと突飛ですけれども、樋口一葉の「たけくらべ」のような少年と少女の話なのですが、決して子供の世界ではない。多分照菊にしても義雄にしても10代後半という設定になっているかと思うのですが、決して今の10代後半のようには役が描かれていません。今の子供映画、青春映画と違った形で描かれているところが、結構新鮮な驚きを与えてくれている作品ではないかと思います。」
柳下 「成瀬監督の作風で好きなところは、すべての人を割と平等に、温かい目で見ているところです。また、自立した女とダメ男という関係が描かれています。この頃の日本の映画監督は男性で、女性は従うという描かれ方が多い印象なのですが、成瀬監督の描く女性は大概、外で働く職業婦人です。」
大久保 「そうですよね。この作品でも河村黎吉さんが、本当に頼りない父親ですよね。昼間からお酒ばかり呑んでいます。義雄のほうも結構堕落しているところがありますし、成瀬作品には、カッコいい男性が颯爽と活躍することがない気がします。ただ、柳下さんが温かい視点だとおっしゃっていましたが、私は少し違った感じを持っています。平等な視点ではあるのですが、温かいというよりは、とてもペシミスティックなところがあって、それが映画の中でずっと通奏低音みたいな形で漂っているような気がするのですよね。」
柳下 「ピアノdeフィルムvol.11で『限りなき鋪道』を上映しましたが、ペシミスティックではあるのですが、自分を鼓舞するような台詞もあって、どん底に堕ちるところをなんとか奮い立たせるみたいなところはあるかもしれないですね。」
大久保 「成瀬巳喜男の映画を見て、生きる気力がわき起こることはないかもいれません。しかし、ただ悲嘆に暮れさせるばかりかというと、決してそうでもないですよね。急に状況が回復してくるということもあるわけです。だから『君と別れて』の終わり方も、単に悲しいだけではなく、2人の気持ちがお互いに通じ合っていることがわかるので、非常にすがすがしいような気もします。50年代前半の作品を観ていくと『めし』にしても『稲妻』にしてもぜんぜん問題が解決していないのに、妙に肯定的な描かれ方をして幕を閉じますよね。そのあたりも含めて、楽観と悲観のどちらでもない描き方をしていく監督ではないかなという気がちょっとしています。そこがいいところだなって。」
柳下 「成瀬監督はいつも定時に撮影を終えるのに、こんなに優れた作品を次々と作れるのはどうしてでしょう。」
大久保 「成瀬監督が几帳面な方だったってよく言われているのですけれども、最初からコンテが考えられていたということがあるからかもしれませんね。今残っている資料は少ないものの、世田谷文学館に所蔵されている、成瀬が使っていた『浮雲』の撮影台本を見ていくと、余白の部分に絵コンテがきっちり書いてあったりするので、もうそのとおり撮っていけば終わるっていう感じだったのではないかと思います。現場でも、編集でもあまり迷うことがなかったのではないでしょうか。それと、スタッフが結構固定していたので、撮影は玉井正夫さんが多いですけれども、裏方さんたちと阿吽の呼吸とかがあったので、早かったのかなと思います。ただ成瀬巳喜男に限らず50年代の監督の多くがそういう形で作っていったわけですよね。マキノ雅弘さんなんてとてつもなく早かった。そういう日本の撮影所の体制が支えになっていたという面もあったのではないかと思います。ただ成瀬巳喜男も出来上がった作品はもちろん予定通りに作られているのですが、うまくいかないときもあったのです。例えば『裸の大将』という作品は、準備はしたけれど結局撮ることができなかった。水木洋子のシナリオが遅れ、カラー撮影のためのテストが長くかかり過ぎたということもあり、結局2年くらい撮れないまま時間が過ぎてしまい、結局堀川弘通が監督することになります。なので、毎回毎回うまくいくということではなかったようです。ただ撮り始めればきっちり早く終わった。成瀬は筈見恒夫との対談で『浮雲』は45日で撮影した、通常の場合、撮影期間は32日か33日と言っています。」(成瀬巳喜男・筈見恒夫「成瀬巳喜男・筈見恒夫対談」、『映画ファン』1955年5月号。『映畫読本 成瀬巳喜男』に再録)
柳下 「終了時間になってしまいました。引き続きロビートークを行いますので、ご興味のある方はぜひご参加ください。ありがとうございました。」
終演後ロビーいっぱいにお客様が参加され、本編トークショーの盛り上がりはさらに続き、熱いトークが繰り広げられた。成瀬巳喜男作品における水久保澄子の話、ドリー撮影によるアップなど成瀬監督がこの作品で手掛けた斬新な演出のこと、照菊の気持ちの考察など様々な話が飛び出した。お客様のほうから「しながは」駅の表示が何回も出るのは、反対から読むと「はかなし」となるからではとマニアックな話になると、そういえば菊江(吉川満子)が照菊に「吉川さんが次の部屋でお待ちですよ」という楽屋オチもあったなどと、話は広がっていった。それに対し大久保清朗さんも『めし』では原節子の姪役に『青い山脈』の原節子の役名と同じ島崎雪子が起用されていたと答え、雰囲気は成瀬巳喜男ファンミーティングの様相となり瞬く間に時間は過ぎ、終了したのは15時半、上映開始から3時間も経っていた。
プロフィール
【柳下美恵 (やなした みえ)】
武蔵野音楽大学有鍵楽器専修(ピアノ)卒業。
1995年山形国際ドキュメンタリー映画祭で開催された映画生誕百年祭『光の生誕 リュミエール!』でデビュー。以来、国内海外で活躍、全ジャンルの伴奏をこなす。
欧米スタイルの伴奏者は日本初。2006年度日本映画ペンクラブ奨励賞受賞。 ピアノ(オルガン)を常設する映画館を巡る全国ツアー「ピアノ×キネマ」、サイレント映画の35ミリフィルム×ピアノの生伴奏“ピアノdeフィルム”、 サイレント映画週間“ピアノ&シネマ”などを企画。映画館にピアノを常設する“映画館にピアノを!” の呼びかけなどサイレント映画を映画館で上映する環境作りに注力中。
【大久保清朗(おおくぼ きよあき)】
1978年東京都生まれ。映画評論家。山形大学人文学部准教授
共著:蓮實重彦・山根貞男編『成瀬巳喜男の世界へ』(筑摩書房)、南波克行編『スティーブン・スピルバーグ論』(フィルムアート社)など
訳書:フランソワ・ゲリフ『不完全さの醍醐味―クロード・シャブロルとの対話』(清流出版)
現在「ユリイカ7月号」成瀬巳喜男特集にて『浮雲』についての考察が掲載されています

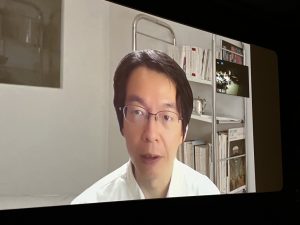

 この記事のライター
この記事のライター