【OAFF】『宇宙探索編集部』孔大山(コン・ダーシャン)監督
アジアの最新映画を紹介する大阪アジアン映画祭。17回目となる今年も3月に開催された。コンペティション部門でグランプリに輝いたのは、他者との接触を好まず、いつも1人で過ごしている女性に起きた変化を描く韓国映画『おひとりさま族』。このほか、アダルトショップでアルバイトすることになった大学生と謎めいたオーナーの交流を描いたモンゴル映画『セールス・ガール』や、香港の大スター、アニタ・ムイの生涯を描いた『アニタ』など、女性が主人公の良質な作品が目立った。
そんなラインナップの中で、宇宙人に魅せられた中年男性が地球外生命体を追ってひたすら旅をする中国映画『宇宙探索編集部』は異質だった。廃刊寸前の雑誌「宇宙探索」の編集者が、宇宙人の仕業だと思われる不思議な現象が起きたという心許ない情報を頼りに、編集部の面々を巻き込んで旅に出るフェイクドキュメンタリー風の作品。SFコメディかと思いきや、ナンセンスな笑いを差し挟みつつ、ひたすら緩く緩く進んでいく。監督の孔大山(コン・ダーシャン)にとって長編デビュー作でありながら、制作会社には大手映画会社が名を連ねている点も興味をそそる。
近年不作の印象がある中国映画界だが、2021年の平遥映画祭で作品賞や観客賞を受賞するなどこれからが期待される才能に、オンラインでお話をうかがうことができた。
――コン監督にとって長編映画デビュー作ですが、制作会社には大手が名を連ねています。この作品の制作の背景を教えてください。
孔大山(コン・ダーシャン)監督:郭帆(グォ・ファン)監督がエグゼクティブ・プロデューサーを務めてくださった関係です。グォ監督が私にこの映画の脚本を書くように言ったのです。完成したものを読んで気に入ってくださり、大手の映画会社を何社も引っ張ってきてくれました。この映画は一見、どんな作品かよく分かりません。低予算の作品で、スターも出演していなければ、派手さもない。それなのに「なぜこんなに多くの大手映画会社が出資したのか?」と観客は関心を持ってくれます。
――ある意味、グォ監督の戦略だったのですね?
コン監督:そうとも言えますね。
――グォ監督は『流転の地球』(2019年)の大ヒットで一躍有名になった監督です。どんな経緯で知り合ったのですか?
コン監督:10年来の付き合いなのです。当時の私は大学生で、韓国のコミックを映像化した短編映画を制作していました(中国語タイトルは「少年馬力傲的煩悩」)。グォ監督もその時、初めての長編映画を制作中で、それが同じ原作だったのです。同じ年(2011年)に完成し、グォ監督がネットで私の作品を見て気に入ってくれたのが出会いでした。その後、グォ監督の作品の監督助理を務めるなどしていました。
『流転の地球』を撮り終わったあと、グォ監督から何か撮りたいものはないかと聞かれ、『宇宙探索編集部』のアイデアを話したところ、支援してもらえることになったのです。
――もともとSF映画に関心があったのですか? この題材を選んだ理由を教えてください。
コン監督:実はSF映画には詳しくありません。この映画を撮る前から持っていた印象としては、SF映画といわれる作品の9割の内容は本当の意味でSFではなく、特撮映画だということです。『宇宙探索編集部』の脚本を書いた時も、これをSF映画にしようとは思いませんでした。ジャンル的に言えば、ロードムービーだと思っています。それからブラックユーモアも盛り込みました。物語の終盤には、実存主義の答えのような、少しSF的なテーマが入っているかもしれませんが。
――終盤に浮かび上がる「自分が存在する意義」というテーマですね。最初から盛り込もうと思っていたのですか?
コン監督:最初は考えていなくて、第2稿で加えました。脚本で主人公の人物像を練っていくうちに出てきた要素です。
この映画を観た人は皆さん、最初はコメディだと感じると思います。でも厳密に言うなら、コメディではなく不条理劇だと定義しています。コメディ映画のコアにあるのは文字どおり喜劇ですが、不条理劇の場合は悲劇です。この映画は序盤こそ喜劇に見えますが、後半に悲しみを帯びてくるのは、そういう理由です。
――俳優たちの間やテンポが絶妙でした。ドキュメンタリー風に撮ってありますが、かっちり演出を固めてあったのではと想像します。
コン監督:九割方は演出をつけ、残りは俳優たちの現場での反応に任せた感じでしたね。プロの俳優にも、素人の出演者にも、日常の姿と近い状態の演技をしてほしいと要求しました。演技しているようには見せないでくれと。ドキュメンタリー風のスタイルにしているので、村民、通行人に至るまで、メインキャストと同じトーンでないとこの作品にリアリティを持たせられなくなります。俳優たちには難しかったと思います。力の抜けた自然体の状態に見せつつ、脚本が指示したお芝居をこなさなければいけませんから。
――ブラックユーモアが効いていて、そこはかとない笑いを誘う作品でした。こういうノリにしようというインスピレーションはどこから?
コン監督: 私の経験や習慣、関心などから来たものかもしれませんが、ただ、真面目で真剣な人がナンセンスな言動をとる感じが好きなのかもしれません。最近ネットでよく言われる「一本正経的胡説八道」(真面目な顔ででたらめを言う)な感じですね。
――ユーモアのセンスのある方だとお見受けしましたが、どんなエンターテインメントに触れてきたのか興味があります。
コン監督:たぶん多くの同世代と同じく、子供の頃はハリウッド映画や、チャウ・シンチー、ジャッキー・チェンらの香港映画を観て育ちました。映画を学び始めてから、さまざまな国の代表的な作品を見るようになりました。日本映画ではSABU監督の『ポストマン・ブルース』(1997年)が印象に残っています。学校では黒澤明や小津安二郎などの作品を学ぶわけですが、メジャー作品ではない若い日本の監督の作品は、個性的で面白いと思いました。日本のアニメでは湯浅政明監督の作品が一番好きです。こうした非常にパーソナルかつ独自のスタイルを持った監督の作品に影響を受けたと思います。
――ロードムービーだとおっしゃったとおり、主人公たちは中国を西へ西へと旅していきます。ロケ地や撮影期間を教えてください。
コン監督:撮影は北京から始まりました。そこから本当に列車に乗って、四川省に入ったのです。映画に登場する列車内のシーンは、本当に四川に向かう途中です。四川省成都に入ってから、同省内のさまざまな所をまわりました。主人公たちが旅の途中に出会う不思議な男スン・イートンがいる村は宜賓市にあります。そこから彝(い)族が暮らす大凉山地区に入りました。かつて三池崇史監督が『中国の鳥人』(1998年)を撮った所ですね。それから雅安市に向かいました。ここはスン・イートンを演じた脚本家でもあるワン・イートンの故郷なのです。彼は映画監督でもあります。彼が地元のいろいろな場所を紹介してくれて、四川省各地で撮影してまわりました。車で移動して、途中下車しては撮り、撮り終えると次の撮影地点に移動する。撮影チームというより旅行団のようでしたね。撮影期間は全部で37日間だったのですが、非常に慌ただしかったです。
――何人くらいのチームで移動したのですか?
コン監督:80人前後です。この映画を観た人は、数名のカメラマンやスタッフだけの、ものすごい少人数で撮ったように感じると思いますが、映画づくりを知っている人なら、適当に撮ったように見える作品でも数多くのスタッフがバックにいて出せた効果だと分かるはずです。
――初の長編監督映画で、責任も大きかったと思います。どのようにしてこの役割やプレッシャーを乗り越えたのですか?
コン監督:プロジェクトの最初に私が考えたのも、この問題でした。それまでたくさん短編は撮っていましたが、この規模の映画は初めての経験だったからです。おまけに、何か所もロケ地をまわりながら撮らなければいけない。友人やスタッフからは、ベテラン監督でもチャレンジングな撮影だと言われました。
そういうわけで、予想どおり撮影中はさまざまな困難に直面しました。カメラマンはベルギー人なのですが、彼に「この映画の英語タイトルは有名な中国の小説『Journey to the West』(西遊記)だ」と説明したことを覚えています。1つの物を求めて困難な旅に出る一団の物語で、彼らは81の大難を経験して目的を果たすのだ、と。だからトラブルに見舞われた時は、「81個に近づいているぞ。成功にまた一歩近づいた」と考えるようにしようと話していました。
――中国での公開日は決まりましたか?
コン監督:まだはっきり日程は出ていませんが、年内には公開できると思います。
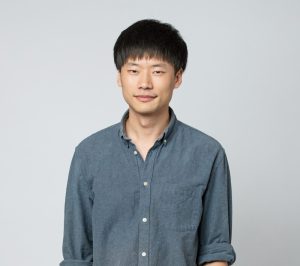

 作品情報
作品情報 この記事のライター
この記事のライター